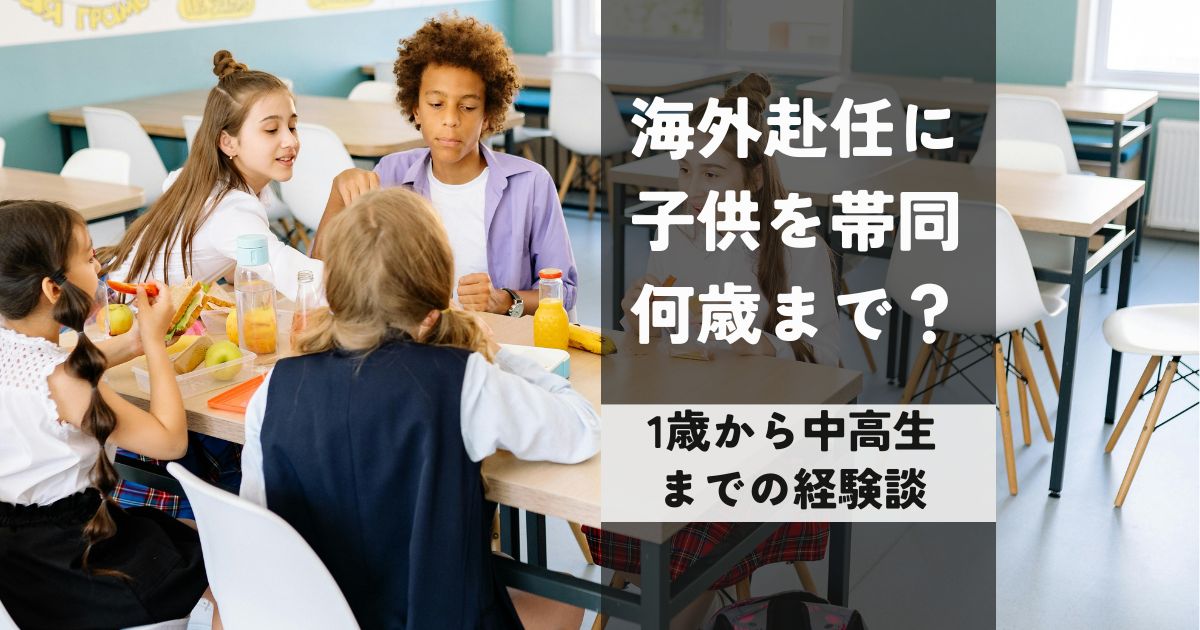海外赴任が決まった!子供の帯同は何歳までがおすすめ?

うちの子と同じ歳の子供を海外に帯同した経験談を知りたい!

現地校の学習についていける?英語習得できる?友達できる?帰国子女受験は?

この記事ではアメリカ赴任に2回子供を帯同した経験から、上記の疑問について考えていきます!

こんにちは。けいちょこです。
2人の子供を連れて、2回アメリカに住んだ経験があります。
1回目の渡米では、
1歳未就園児からプリスクール(幼稚園)、キンダー(年長)、小学校(エレメンタリー)
2回目は、中学校(ミドルスクール)、高校(ハイスクール)
それぞれの年齢で様々な悩みに直面しました。
海外赴任に子供を帯同するか、子供を帯同するなら何歳がベストか、正解は子供一人ひとり、家庭によって違いますよね。
でも、この5つの軸で考えるとちょっとは整理できます。
ポイント
・現地校の学習/日本の学習
・英語(現地語)習得/日本語(母語)維持
・友達
・健康/生活
・帰国子女受験
バイリンガルになるには何歳までがベスト?とか、10歳ギリギリ説なんかもありますよね。
語学習得の面だけでなく、子供の成長や海外で直面する悩みについて、実際に経験してわかったことを具体的に書いています。
※この記事では海外赴任に子供を帯同して現地校に通う場合について書いています。

「目次」を開くと読みたい年齢にジャンプできます!チェックリストは「まとめ」にジャンプしてください。
海外赴任に子供を帯同するなら何歳まで?
実際に経験してわかったことを
未就園児
幼稚園〜小学校低学年
小学校高学年
中高生
にわけてお伝えします!
未就園児

未就園児を海外に帯同する場合、
早すぎる?母語は?英語は?病気は?いろいろ心配ですよね。
上記5つのポイントで、子供が小さいころ特に気になるのがこの3つ👇
・現地校の学習/日本の学習
・英語(現地語)習得/日本語(母語)維持
・友達
・健康/生活
・帰国子女受験
特に母語の基盤作りは家庭の介入が欠かせません。
語りかけ育児を意識するのはもちろん、幅広い日本語に触れるために
・読み聞かせ
・日本人グループで遊ぶ
・日本語補習校の幼稚園(3歳〜)
これらで日本語の基盤作りをしました。
英語に関しては、うちは英語より日本語重視だったけど、それでも現地の幼稚園に通うようになったら会話できるようになりました。
この年代の課題は帰国後の英語力維持です。
うちは英語維持を特にせず、帰国後新しいお友達とのびのび遊んだのであっという間に忘れました笑

でも小さい頃の海外生活が、小学生になってからの英語への興味のきっかけになりました。
日本語も英語も言語発達や教育効果については個人差が大きいので、焦らずサポートが大切です。
海外で過ごす期間の長さも言語の習得には影響が大きいですよね。
友達については、うちは日本語をしっかり身につけてほしかったため日本人のプレイグループに入って遊んでいました。
それ以外は家の前で近所の子と遊んでいました。
子どもが小さいうちは環境変化や英語に対する心理的抵抗感の低さが良い方向に働き、英語が話せなくても一緒に遊べて楽しく過ごせました。
でも!!情けないことに私自身は英語が苦手で、現地のママとの会話はいつも大変でした。
話についていけなかったり、何か言ってみたら話が理解できなくて困らせてしまったり。
それでも子供の成長や地域のことなど少し話せて楽しかったです。
このとき私は地域のESLに通っていたのですが、英語はあまり上達しませんでした。
2回目の渡米時に知ったこのオンライン英会話をやっていたら、もっと楽しいアメリカ生活を送れたはず。
小さい子連れは現地の人と交流する機会がたくさんありますよ〜。
そして、この時期の心配事といえば病気やケガ。
小児科や救急対応できる病院探しは必須です。
うちは最初に行った病院がイマイチで…でも信頼できる病院を見つけて、慣れない海外生活でも少し安心できました。
幸いアメリカ在住中に大きな病気やケガはありませんでしたが、検診や予防接種など小児科には何度も通いました。
この時期の海外での子育ては、頼れる親族もいないし外に出れば英語の世界なので大変ですが、家族で一緒に過ごせて楽しいこともたくさん経験しました。

残念ながら子供はあまり覚えてないですが笑
幼稚園 / preK / キンダー/ 小学校低学年

海外赴任に幼稚園〜小学生低学年で帯同した場合、
日本語と英語はどうなるの?親が英語苦手だけど、大丈夫?とかいろいろ心配ですよね。
先ほどの5つのポイントで考えていきます。
・現地校の学習/日本の学習
・英語(現地語)習得/日本語(母語)維持
・友達
・健康/生活
・帰国子女受験
まず現地校の学習と英語ですが、アメリカではこの時期に英語の基礎を学習するため現地校に通うことで英語が身につきやすいです。
授業も基礎の段階なのでそれほど難しくなく、学習面も追いつきやすい年齢です。
我が家の場合はキンダーの1年間でESLクラスを卒業して、小学校1年生ではネイティブ同年代の中でも英語力が上のレベルに成長しました。
でも最初は英語がわからなくてツラい…。
毎日の読書習慣を続けることで英語力がグングン伸びるし、帰国後も維持しやすくなります。
毎週のように図書館に通って大量に本を借りていました。
「子供は英語にすぐ慣れる」はウソだけど乗り越えられます。
日本語については、英語力の成長を喜んで日本語を放置すると特に読み書きの力が落ちやすいので注意が必要です。
うちは日本語補習校+図書室で本を借りて、短時間でも毎週一緒に宿題をやることと、日本語の本を読むことを続けました。
日本との学習ギャップについては、補習校やタブレット学習などで帰国後の学習に備えておくと安心です。

アメリカではZ会のタブレット学習を利用していました。
公式サイトはこちら→Z会の通信教育
言語発達や教育効果については個人差が大きいですよね。
だからこそ家庭での習慣づくり、読書や親の関わりが重要になります。
友達もこの時期は作りやすいです。
この時期は公園で「一緒に遊ぼう」と現地の子供達からよく声をかけられました。
また習い事など好きなことも見つかって、学校の外でも友達ができました。
でも!!情けないことに私自身は英語が苦手で、現地のママとの会話はいつも大変でした。
話についていけなかったり、何か言ってみたら話が理解できなくて困らせてしまったり。
それでも子供の成長や地域のことなど少し話せて楽しかったです。
先生や現地ママからバンバン届くメールは翻訳アプリを使ったり、伝えたいことは事前にテンプレ英文を作ってから挑戦したり。
完璧じゃなくても準備すれば、英語が苦手でも子供のサポートはできます。
このとき私は地域のESLに通っていたのですが、あまり英語は上達しませんでした。
2回目の渡米時に知ったこのオンライン英会話をやっていたら、もっと楽しいアメリカ生活を送れたはず。
子連れは現地の人と交流する機会がたくさんありますよ〜!
そして、この時期の心配事といえば病気やケガ。
小児科や救急対応できる病院探しは必須です。
うちは最初に行った病院がイマイチで…でも信頼できる病院を見つけて、慣れない海外生活でも少し安心できました。
中学高校の帰国子女受験は、学校によって要件(在外期間、帰国後年数)が違うので学校ごとに確認が必要ですが、小学校低学年の頃に海外で過ごしていた時期があれば帰国子女枠での受験が可能な学校もあったりします。
アメリカに引っ越したり日本に帰国したりという環境の大きな変化に柔軟に対応するのは、低学年の子供でも大変です。でも高学年以上になってからより圧倒的にハードルが低いです。またこの時期にアメリカで過ごしたことで子供はネイティブの発音を身につけ、読み書きもできるようになって帰国後の英語維持につながりました。
小学校高学年

海外赴任に小学生高学年で帯同した場合、
現地校の授業ついていける?友達できる?帰国受験、大丈夫?いろいろ心配ですよね。
先ほどの5つのポイントで考えていきます。
・現地校の学習/日本の学習
・英語(現地語)習得/日本語維持
・友達
・健康/生活
・帰国子女受験
小学生高学年の現地校の授業は授業内容も英語も難易度めちゃくちゃ高いです。
先生もクラスメイトも全員超絶早口、優しくいろいろお世話をしてくれる人なんていません(笑)
長文読解、要約、論理的なライティングなどなど、学校生活に慣れてきても学習面はなかなか追いつけずずーっと大変!
宿題を一緒にやろうと思っても、授業が理解できてないからまずは授業の復習から。
毎日今日は宿題が終わるのに何時間かかるんだろうと、不安になりました。
それでも毎日諦めずに頑張っていると、成績は全教科Aをとっていつの間にかクラスメイトから頼られる存在に。
渡米して1年過ぎたあたりから一人で宿題ができるようになって、2年でESLを卒業できました。
学習面は本当に大変だからサポートは必須!
親のサポートが難しい場合は、現地のチューターやオンライン家庭教師の検討をおすすめします。

家庭教師サービスではないですが、オンライン英会話のワールドトークは講師が日本人で、日本語で質問したり解説してもらうことができます。さらに指定テキストやカリキュラムがないので現地校の授業の復習や宿題の相談が可能です。
対応してもらえるかどうかは講師によりますので、まずは相談してみてください。
海外在住の講師も在籍しており、海外に住んでいても日本との時差を考えず都合の良い時間にレッスンできるところもポイント高いです。
日本の学力の維持は、この時期の大きな課題です。
現地校が大変なのに日本語の補習校にも通って宿題もするとなると、かなりキツいです。
でも日本の学習を放置すると特に算数と読み書きの力が落ちやすく、帰国後に負担になるので注意が必要です。
うちは日本語補習校+読書+タブレット学習で帰国後の学習に備えることができました。
読書はこちらを利用して、アメリカに住んでいても日本の本を好きなだけ読めるようにしました。
Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック

タブレット学習はアメリカではZ会を使っていました。
公式サイトはこちら→Z会の通信教育
言語発達や教育効果については個人差が大きいですよね。
だからこそ家庭での習慣づくり、読書や宿題に一緒に取り組むなど親の関わりが重要になります。
友達を作るのは、低学年の頃よりちょっとハードルが上がる印象があります。
友達ゼロの時期はツラい。
だからこそ高学年以降の海外帯同は本人の意思が重要です。
我が家の場合は日本人がほとんどいない環境でしたが、他の国からの転校生もいて、英語の習得に合わせてネイティブの友達もできました。

スポーツや音楽、勉強など得意分野があると友達の輪が広がります!
子供は地域のスポーツチームや音楽の活動を通して友達が増えました。
習い事など親が得意なこと、好きなことができる場所を探してあげること、少しでも不安を解消するために子どもの話をよく聞くことで、安心して挑戦できる環境を整えてあげることが大切です。
私自身は英語が苦手で現地のママとの会話はいつも大変だったのですが、こちらのオンライン英会話で英語習慣を身につけて少しずつ言いたいことが言える回数が増えていきました。
アメリカの中学校はできる人、やる気のある人はどんどん挑戦できる環境があるので、情報収集が大切です。
もし親が英会話力ゼロなら一歩進むだけでも、手に入る情報が変わってきます。
拙い英語でも親同士の会話から知ることが結構ありました。
学校の先生とはメールベースでのコミュニケーションで、子供が自分で伝えられる年齢になっているので、親の英語力が低いことで困ることはありませんでした。
また、小学生高学年のこの時期は中学受験を考えている方も多いです。
帰国子女受験の場合、学校によって要件(在外期間・帰国後年数)が違うので学校ごとに確認が必要です。
要件によっては帰国子女枠で受験できない学校も。
帰国子女受験を考えている場合は、海外に行くタイミングや帰国のタイミングなどが影響するため早めの情報収集が大切です。
帰国子女受験に向けて
英語:現地校で伸ばす
日本の学力:補習校・タブレット学習・家庭教師
エッセイや面接:日々の親子の会話が役立つ
英語の資格:英検・TOEIC・TOEFLなどの対策
帰国子女受験対策として、オンライン家庭教師を利用することもできます。

完全オーダーメイドの指導システム【家庭教師のサクシード】 は、帰国子女や留学・海外転勤などの経験がある先生が多数在籍していて、帰国子女受験合格に向けてサポートしてくれます。
講師数も多く、プロ講師指定・出身校指定・女性講師指定など希望できます。
公式サイトはこちら↓
>>> 上場企業が運営する安心の家庭教師【家庭教師のサクシード】
![]()
帰国子女受験には英語の資格が必要になることが多いです。
海外での英検受験は試験会場が限られているため受験するのが大変です。
遠方の場合は家族旅行のような感じで受験する人もたくさんいます。
現地で受験するならTOEFLなど別の資格試験の方が受験しやすいです。
小学生高学年以上での海外帯同は、小さい頃の海外生活以上に本人の意思次第で良い経験にも、残念な経験にもなります。アメリカのミドルスクールでの経験は、日本人としてのアイデンティティーがある程度育っている中で海外生活を送ることで感じることもたくさんあり、日本とは違う教育を受け、アメリカにいるからこその新しい挑戦もすることができました。 2年程度と短い期間でしたが、たくさんの友達と楽しい学校生活を送り、そして帰国後は自分の意思で英語力を伸ばす努力をできることがこの時期のメリットの一つだと感じています。親も一緒に頑張る気持ちを持つことで、勉強や友達の悩みを乗り越えられます。
中学生・高校生

中学生・高校生を海外赴任に帯同した場合、
実際どうなの?友達できる?進路どうする?いろいろな不安がありますよね。
先ほどの5つのポイントで考えていきます。
・現地校の学習/日本の学習
・英語(現地語)習得/日本語維持
・友達
・健康/生活
・帰国子女受験
中高生の現地校の授業は、授業内容も英語も難易度めちゃくちゃ高いので本気で覚悟して帯同してください(笑)
ツラい時期は必ずあるから、中高生の海外帯同は本人の意思が重要。
本人が望んで海外に行けば、苦しくても乗り越えるために努力できるはず。
帯同する場合、親ができることは、子供の意思を尊重しつつ一緒に不安を乗り越える伴走者になること。
アメリカ現地校のハイスクールは先生もクラスメイトも超絶早口で、そのうえ塩対応。
それでも授業はほぼグループワーク&ディスカッション。
授業のディスカッションのために毎日膨大な英文を読んだり、動画を見て予習が必要で、翌日もまたその繰り返し。
一緒に宿題に取り組みながら今日は宿題が終わるのに何時間かかるんだろうと、毎日不安でした。
それでも諦めずに頑張っていると、成績は全教科Aをとってクラスメイトからいつの間にか頼られる存在に。
だんだん一人で宿題ができるようになって、1年でESLを卒業しました。
学習面は本当に大変だからサポートは絶対必要!
親のサポートが難しい場合は、現地のチューターやオンライン家庭教師の検討をおすすめします。

家庭教師サービスではないですが、オンライン英会話のワールドトークは講師が日本人で、日本語で質問したり解説してもらうことができます。さらに指定テキストやカリキュラムがないので現地校の授業の復習や宿題の相談が可能です。
対応してもらえるかどうかは講師によりますので、まずは相談してみてください。
海外在住の講師も在籍しており、海外に住んでいても日本との時差を考えず都合の良い時間にレッスンできるところもポイント高いです。
日本語の維持はそれほど心配しませんでしたが、日本の学力の維持はこの時期の大きな課題です。
現地校が大変なのに日本語の補習校にも通って宿題もするとなると、かなりキツいです。
でも日本の学習を放置すると特に数学と読み書きの力が落ちやすく、帰国後に負担になるので注意が必要です。
うちは日本語補習校とタブレット学習で帰国後の学習に備えました。

タブレット学習はアメリカではZ会を使っていました。
公式サイトはこちら→ Z会の通信教育
言語発達や教育効果については個人差が大きいですよね。
だからこそ宿題に一緒に取り組むなど親の関わりが重要になります。
友達作りは、授業ごとにクラスメイトが変わること、グループワークが多いことで友達を見つけやすいです。
日本人はほとんどいない環境でしたが、南米やヨーロッパ、アジアなど他の国からの転校生とは友達になりやすいです。

スポーツや音楽、勉強など得意分野があると友達の輪が広がります!
子供は部活や音楽の活動を通して友達が増えました。
親が得意なこと、好きなことができる場所を探してあげること、少しでも不安を解消するために子どもの話をよく聞くことで、安心して挑戦できる環境を整えてあげることが大切です。
私自身は英語が苦手で現地のママとの会話はいつも大変だったのですが、こちらのオンライン英会話で英語習慣を身につけて少しずつ言いたいことが言える回数が増えていきました。
アメリカの高校はできる人、やる気のある人はどんどん挑戦できる環境があるので、情報収集が大切です。
もし親が英会話力ゼロなら一歩進むだけでも、手に入る情報が変わってきます。
拙い英語でも親同士の会話から知ることが結構ありました。
学校の先生とはメールベースでのコミュニケーションで、子供が自分で伝えられる年齢になっているので、親の英語力が低いことで困ることはありませんでした。
また中高生のこの時期は帰国子女受験を考えている方、多いですよね。
帰国子女受験の場合、学校によって要件(在外期間・帰国後年数)が違うので学校ごとに確認が必要です。
要件によっては帰国子女枠で受験できない学校も。
突然帰国が決まって高校生の子供が日本で通う学校がない、という事態は絶対に避けたいです。
日本への帰国時期がいつ頃になるか、時期がズレる可能性があるのか、ズレたらどうするのかなど考えておく必要があります。
実際に、帰国時のことをあまり考えず海外生活を送っていたらお子さんが高校生になって帰国が決まり、日本での受け入れ先が見つからず苦労されている方もいました。
日本の高校への編入は元から枠が非常に少なく、タイミングによってはゼロの時もあります。
日本での進学先の情報収集は早めにしておきたいです。
帰国子女受験に向けて
英語:現地校で伸ばす
日本の学力:補習校・タブレット学習・家庭教師
エッセイや面接:日々の親子の会話が役立つ
英語の資格:英検・TOEIC・TOEFLなどの対策
帰国子女受験対策として、オンライン家庭教師を利用することもできます。

完全オーダーメイドの指導システム【家庭教師のサクシード】 は、帰国子女や留学・海外転勤などの経験がある先生が多数在籍していて、帰国子女受験合格に向けてサポートしてくれます。
講師数も多く、プロ講師指定・出身校指定・女性講師指定など希望できます。
公式サイトはこちら↓
>>> 上場企業が運営する安心の家庭教師【家庭教師のサクシード】
![]()
帰国子女受験には英語の資格が必要になることが多いです。
海外での英検受験は試験会場が限られているため受験するのが大変です。
遠方の場合は家族旅行のような感じで受験する人もたくさんいます。
現地で受験するならTOEFLなど別の資格試験の方が受験しやすいです。
またアメリカ現地校での成績も評価されます。
1年目からA評価を取るためのアメリカの成績攻略法はこちらで解説しています。
中学生高校生での海外帯同は、小さい頃の海外生活以上に本人の意思次第で良い経験にも、残念な経験にもなります。アメリカのハイスクールでの経験は、日本人としてのアイデンティティーがある程度育っている中で海外生活を送ることで感じることもたくさんあり、日本とは違う教育を受け、アメリカにいるからこその新しい挑戦もすることができました。2年程度と短い期間でしたが、アカデミックな英語力を多少身につけることができ、日本でやってきたことを活かしてアメリカでも自分らしく過ごすこともできました。そして帰国後は自分の意思で英語力を伸ばす努力をできることがこの時期のメリットの一つだと感じています。親も一緒に頑張る気持ちを持つことで、勉強や友達の悩みを乗り越えられます。
まとめ|最適な年齢より家庭の準備が大切
子どもを海外に帯同するなら何歳まで?…親として悩みますよね。
でも、その答えは年齢で一律に決められるものではないので
現地と日本の学習
母語の維持と第二言語の習得
友達関係
健康・生活
帰国子女受験・進路
いろんなことを考えて、家族にとって、子供にとって良い選択ができることを願っています。
教育効果や言語習得は個人差が大きいからこそ、親のサポートや家庭での工夫が子どもにとって大きな支えになります。
そして、厳しい時期を乗り越える力は子どもの「自分でやってみたい」という意思から生まれます。
最後に、海外赴任に子供を帯同するときのチェックリストを作成しました。
どの年齢であっても、家族で準備を重ね、子どもの声に耳を傾けて一歩ずつ進めば、帯同するかしないかはきっと「納得できる選択」になります。